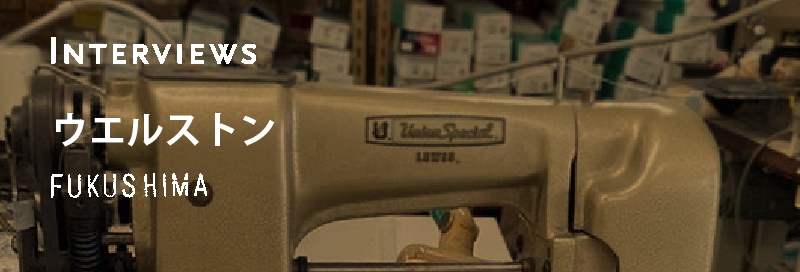2025-26年秋冬シーズンのルックブックを担当したのは、スタイリストの飯島朋子さん。それぞれ異なる立ち位置から、長くファッションに携わってきた2人。だが、ものづくりへの想いは「似ている」と口をそろえる。そんな2人が語り合う、「続けることの面白さ」とその先について。
「好きなものを続けることって、実は難しいと思います」(飯島)
加藤:飯島さんに初めてお会いしたのは、私がまだPRをしていた頃ですから、もう20年以上前になりますよね。
飯島:そうですね。当時はスタイリストとして独立したばかりで、まだ全然売れていなかった時代です。その後、加藤さんがプレスを辞めてブランド(UNION LAUNCHの前身ブランド)を立ち上げるときも、ちゃんとご連絡をいただいて。
加藤:あの頃からのお付き合いですが、ルックの撮影をお願いするのは今回で2回目ですよね。コロナ禍前にお願いしたときのことを、よく覚えています。
飯島:ちょうど東京オリンピックスタジアムを建設している最中で、あの周辺で少し外に出て撮影しました。あらためて振り返ると長いですが、ブランドを継続していくうえで、トレンドを追いかけたり、変化を求められたりするのと、自分の「好き」を貫くことを比べると、私は後者のほうがずっと難しいと思っていて。それをやり続けているのが、加藤さん。作るものすべてに、加藤さんらしさがあるなと思います。
加藤:作り手として進化しなきゃと思う一方で、私はどうしても「できないな」ってなっちゃうんですよね(笑)
飯島:続けていくことを「難しい」と感じていないからこそ、できるんでしょうね。もし難しいと思っていたら、成績やセールスばかりを気にしてしまうようになる。私自身がそうでした。独立した頃は“かわいい”が全盛の時代で、私はまったくそういうものが作れなかったんです。その頃から一貫して“ジェンダーレス”なスタイルを発信していて。20年後にようやくそんな時代が来て、いまはその言葉すら、枠を固定するとして問題視されるほど。“女の子=かわいい”が当たり前だった時代にそれでも続けてこられたのは、人とのつながりがあったからだと思います。「モデルページは難しいけれど、物撮りなら」と、最初は人柄で声をかけていただくことが多かった気がします。
加藤:それを撥ね返せた原動力って、なんだったんでしょう?
飯島:やっぱり、気にしてなかったんでしょうね(笑)。若さもあっただろうし。いまあらためて同じことをやれと言われたら、経験があるぶん逆にできないかもしれません。でも当時は、「だって好きなんだもん」だけで突き進んでいました。
加藤:わかります。私も前身ブランドの頃は、とにかく自分の世界観だけで完結していたと思います。でも、UNION LAUNCHとして新たにスタートしたときは、服づくりに対する考え方そのものを見直しました。自分のデザインを追求するよりも、作る相手のことを考えて、一緒にどう取り込んでいくか。共にものづくりをしていくブランドとして、再スタートを切ったんです。会社と契約して働くのも本当に久しぶりで、正直、途中でリタイアしてしまうかもと思っていました。でも、周りのスタッフがとても協力的で、いろんなご縁にも支えられて。気がつけば、来年で10周年を迎えます。
飯島:もうそんなに経つんですね。
加藤:はい。富山に移住したのが、UNION LAUNCHを立ち上げる一年ほど前。ちゃんとした“田舎”での暮らしは、自分のなかで想像がつかなかったんですが、もう10年。いまでは第二の故郷になっています。
飯島:すっかり富山が拠点ですよね。
加藤:そうなんです。富山に住みながら、たまに仕事で東京にくるスタンス。好きだから続けていられるんだと思うし、逆にそれ以外の振り幅がないから、順応できない(笑)。本当に、飯島さんと似ています。
飯島:よく「芯が強い」とか言ってもらえるけど、違うんですよね。不器用なだけ(笑)
加藤:それ、すごくわかります(笑)。でも、飯島さんが自分の世界観をずっと貫いているのは、本当にすごいなと思います。
飯島:それはやっぱり、自分の“基礎”があるからじゃないかな。加藤さんのブランドを見ていても、ちゃんと土台となるものがありますよね。スタイル一貫しているように見えても、加藤さんの気分が変わることでニューシーズンが始まる。誰かに合わせるんじゃなくて、加藤さん自身が感じたことがそのまま“新しさ”になるんですよね。そういうところが、加藤さんのものづくりの好きなところだし、自分と少し似ているなとも思います。
加藤:うれしいです。
「現場の職人さんたちが、ものづくりを教えてくれました」(加藤)
飯島:仕事のスタンスやスタイリング自体は全然変わらないんですけど、年齢を重ねたことで、“スタイリスト”という仕事への考え方はかなり変わりました。以前は「スタイルはこうあるべき」「服はこう着るべき」と、誰に言われたわけでもないのに、勝手に縛られていたんです。でもいまは、究極、誰か他の人がスタイリングしてくれたとしても現場は成り立つと思っていて。スタイリングをすることだけが、スタイリストの仕事ではないと思えるようになったし、もっと緩くなったというか、楽になりました。いちばんの使命は、楽しくて、みんなが「ああ、良かったね」って思って帰れる現場をつくること。それだけなんです。
加藤:今回の撮影でも、規定サイズのバナーをどうしてもひとつ作らないといけなくて。そうしたら飯島さんが「こういうのがいいと思いますよ」って、その場で作ってくれたんですよね。それがすごく可愛くて、「すみません、それをそのままいただいてもいいですか?」って(笑)。もちろん、スタイリングに特化したスタイリストさんも素晴らしいけれど、飯島さんのように、第一線で活躍している同世代の方たちって、本当に引き出しが多いなと感じます。今回のルックも、ざっくりと気分だけお伝えして、あとはスタイリングから小道具までお任せ。もともと、どこかに少し“不良っぽさ”を感じさせながら、いい意味で力の抜けた飯島さんのスタイリングが、私はすごく好きなんです。だから、細かい打ち合わせをしなくても、二言三言で伝わる心地よさがありました。
飯島:自分と真逆を求められると生みの苦しみを味わいますが、加藤さんの作る服は、自分自身も好きなスタイルなので考えなくてもできる。私はいつも「自分のスタイリングは方程式、数学だ」と言っていて、気分で「これを合わせよう」と決めることはないんです。足し算、引き算でコーディネートを組むから、とにかく早い。コーディネート選手権があったら、多分いちばんになれるくらいのスピード感です(笑)。今回は、加藤さんの服にプレッピーやワークの要素があるから、あえてそこに持っていかず、トラッド寄りにスタイリングしました。基本、“首が詰まっている”感じですね。
加藤:そうなんです、UNION LAUNCHの服は首が詰まりがち(笑)。クルーネックのトワルを組むときも、頭が通るギリギリを狙ってしまう。ボートネックでも、「首にふれてもいいかな」というくらいの詰まり具合が好きで。
飯島:そこにさらにニットを重ねて、もっと詰めました(笑)
加藤:本当に小さなブランドなので、できることは限られていますが、そのぶんバスクシャツのような定番アイテムも、原料や素材までこだわって作っています。昔からデッドストックの生地も好きで、使うことが多いですね。もう廃業されてしまったんですが、90歳近い元機屋さんがいて。その方も生地好きで、あちこちで集めた素材を、忘れたころに広告の裏に貼ってスワッチにして送ってくれるんですよ。それを大事に取ってあって、タイミングを見て「今回、これを使いたいです」と連絡して、やり取りが始まるんです。保管の状態が悪いものもあるので、検反には時間もお金もかかるんですよね。それでも、そういう背景を持ったものを使っていくことこそ、UNION LAUNCHらしさだと思っていて。あとは機屋さんと相談しながら、オリジナルの素材づくりにも力を入れています。今季は、秋冬シーズンには使われなくなってしまう麻を、どう取り入れられるかに挑戦しました。農家と同じように、生産者がわかるものづくりを続けたい。その想いを大切にしています。
飯島:歳を重ねていちばん良かったと思うのは、「大量生産だから」とか「流行っているからいい」とされるものを、まったく気にかけず排除できるようになったこと。むしろ、何かにこだわっている人と、一緒に何かできるようになったことです。農家であれ業者であれ、大量に出してしまうと、そのこだわりは伝わりにくくなりますよね。「すごいいい生地なんだよ」と言われても、数は少なくても丁寧に数点だけ作ったものの方が、私だったらうれしいし、選ぶ視点でもそういう姿勢に惹かれるなと思います。
加藤:私はバイイングからスタートしたので、最初は自分が服を作る人になるなんて1ミリも考えていませんでした。でも、真剣にやってみようと思ったのは、あるブランドのディレクションを任されたときに、その会社の求める方向性と全然シンクロしなかったんですね。「なぜ私をディレクターに?」って思ったくらい。そのときに、やっぱり自分でちゃんとリスクを背負って、一度きちんとモノづくりをしてみないとダメだと決意しました。それこそ最初は、紹介してもらって、東京の下町にあるメンズのジャケット専門の芯地屋さんを「トントン」と訪ねて。「ここから勉強した方がいいよ」と言われて、ジャケットの裏地を取って、内容物を全部見せてもらいながら教わったんです。
飯島:実践で勉強したんですね。
加藤:仕様についてもわからないことだらけで、すべて工場の職人さんたちに教えてもらいました。UNION LAUNCHのパタンナーも、年配の男性にメインでお願いしているんですが、いまもずっと一緒に学ばせてもらっています。自分のなかでようやく理解できたなと思えたら、そこからやっと次の何かを作ってみようかと一歩ずつ。だから、あまり変わらずやっているのかもしれません。
飯島:でも、それがいいんだと思います。変わらないでいてほしい。
「ひらめきがすべて。若い人たちに自由に楽しんでほしい」(飯島)
加藤:いま自分の拠点が地方にあって、まったく異なるフィールドの方々と出会う機会が増えたんです。そういう人たちと、自分のこれまでのキャリアを生かして何か一緒にできたらいいなと思っていて。撮影のときにも飯島さんにお話ししましたが、街づくりの一環として古民家再生に取り組みたいと考えていて、いま少しずつ進めているところです。昨年6月には富山でイベントを開催したんですが、地方でもこんなに人が集まるんだという手応えが本当にあって。みんなで考えながら、一緒にものづくりができたらいいなという思いと、人とのつながりから新しいことが生まれいく、そんな空間をきちんと形にしていきたいなと願っています。
飯島:いいですね。私もスタイリストとしてやっていくのは、おそらくもうそんなに長くはないだろうなと思っています。最近、若い世代が行き詰まっているという話をよく耳にしていて。後輩たちに道を譲る意味でも、私もどこかで区切りをつけないといけないなと感じています。いまはカウントダウンのような気持ちで、やり残しがないように仕事に向き合っていて。40代からは恩返しだなって。これまでお世話になった人や、関わってきた仕事に対しての恩返しの気持ちでやっています。だから、「もっと自分を表現したい」といった不満も一切ない。昨日や今日に独立したばかり、それくらいの感覚で毎日仕事をしています。
加藤:そういう飯島さんだから、みんなが声をかけたくなるんでしょうね。
飯島:インスタグラムでも、PR的な情報は一切載せていないんです。それよりも、若い人たちが「この業界、面白そう」とか、「ファッションをやってみよう」と思えるように、写真と一緒に制作の背景をテキストにして発信しています。最近は、若い世代のファッション離れがすごいって言われてますよね。だから、こんな風に楽しそうにやっている大人もいるんだよ、と知ってもらったら、興味を持ってもらえるかもしれないと思って始めたんです。実際、それをきっかけにメッセージをもらうことも多くて。若いカメラマンから「この場所はどこで撮ったんですか?」なんて聞かれて、それに答えたりもしています。自分にとっての財産を、分かち合わないといけないなと。だから、自己アピールはなし。「飯島さんでも、こんな悔しい思いをしたり、『やっちゃった』っていう撮影があるんだ」とか(笑)、そういうことも正直に。写真よりも文章を大事にしています。
加藤:スタイリストは体力勝負なところもあるから、「大変そう」というイメージだけが先行するのも困るし、もっともっと多くの人にファッションの世界の面白さを知ってもらいたいですよね。
飯島:私も感じるのは、いまの若い世代は「見たものを模写する力」は本当に優れているんですよ。でも、ゼロから何かを生み出すことには不安があったりする。そこに楽しさを見いだせないと、たぶん長くは続かないんですよね。「これ、かわいい」とか「良くない?」という気持ちだけで発信してもいいと思うんです。でも、いまの若い人たちは最初から、リファレンスやテーマ、資料をきっちり作ってしまう。加藤さんと私みたいに、感覚で“ツーカー”にお仕事するみたいな場面がなかなかない(笑)。私は、ひらめきがすべてだと思うんですよね。だって、この仕事にはルールなんてないし、なんでもできる世界じゃないですか。真面目であることは良いことなんですけれど、“不真面目”だからこそできる面白いことってたくさんあるんですよ。
加藤:そうですね、私たちの世代はファッションに関わるのは“不真面目な人”ばかりだったから(笑)
飯島:そう。でも本当は、誰でもがその要素は持っていて、明日からでもできる。ただ、やらないだけの話なのかなって。「飯島さんみたいに長くやってるから、できるんですよ」って言われるんですけど、逆に考えたら、私たちがいまだにそんなこと言ってる方が、よっぽどやばいですよね(笑)。でも、若いからこそ何をしても許されるんだから、どんどん自由にやってほしいなと思います。
加藤:飯島さんもこれからも変わることなく、楽しそうに弾けているその背中を、若い世代に、そして私たちにも見せ続けてください。
飯島朋子(いいじま・ともこ)
神奈川県生まれ。2000年に独立、数々のファッション誌や広告などで活躍する。次なるプロジェクトとして、女性たちがかっこよく年齢を重ねていく姿を切り撮った写真集『OBAB』を制作予定。